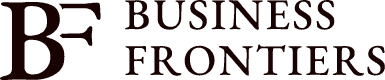9月8日(月)配信 株式会社マインドプラスアカデミーode 代表取締役 下村弥沙妃

三重県出身。大学病院の小児科で白血病をはじめとする小児がん患児の看護に従事。命の現場で「幸せ」や「親子の絆」に向き合う中、心理学を学び、育児アドバイザーとして独立。以降、一万人以上の親子をサポート。心理学・脳科学・量子力学などを融合した独自の育児メソッドを確立し、全国でセミナー・講演活動を展開中。
笠井:紺のジャケットで、若々しい社長さんでいらっしゃいますが、今日はどちらからおこしですか?
下村:ありがとうございます。名古屋から参りました。 笠井:株式会社マインドプラスアカデミーodeですが、どのようなお仕事ですか?
下村:株式会社マインドプラスアカデミーodeの“ode”は、音楽用語で自由形式の頌歌という意味があります。喜びの歌という意味もありまして、一人一人の命を輝かせる、喜びにあふれた自由で、奏でるような人生を手伝いしたいという意味で、社名につけました。
笠井:そうですか。育児セミナーを行なっていると聞きました。
下村:私はもともと小児科の看護師で、小児科のお子さんが多く入院される病棟にいました。そこで、誕生から看取りまで経験をさせていただき、「できるところに目を向け、幸福度を上げるというお手伝いをしたいな」と思ったのがきっかけです。体の病気や環境など、全ては選べませんが、心の在り方や、そこに影響を与える親子関係は、工夫・改善できるというところに気づき、今は子育てに注目し、活動しています。
笠井:これまでの経緯を拝見しますと、白血病をはじめとする小児がんのお子さんがいらっしゃる大学病院の小児科で、看護師さんとして働き、その後、心理学を学んで育児アドバイザーとして独立されています。独自の育児メソッドを確立して、全国でセミナー、講演活動を展開していらっしゃるということなのですが、この育児セミナーが口コミで2年半待ちに
なったと伺いました。
下村:ありがたいことに、たくさんの人から申し込みがありました。

笠井:どのような育児セミナーなのですか?
下村:子どもを一人の人間として注目して、その存在価値を認めるというものです。子どもとして扱わず、性別や国籍、宗教、年齢を超え、本来の人間の本質を伸ばそうということに特化しています。ちょうど育児セミナーを始めたときに、私の子育ても始まったのですが、「我が子がなんだか面白い育ち方をする」ということで、周りの人から声をかけていただくことが増え、そこからお仕事につながりました。
笠井:今の子どもは親がレールを敷いたところを導かれてる子が多いですよね。指示待ちの子は多いと思うのですが、どういう声かけが良いのでしょうか?
下村:いろいろなテクニックがあるのですが、例えば、「親の価値観を伝えない」ということです。評価しない、価値観を与えないことを徹底すると、それを踏まえた声がけになります。例えば、自分から宿題をやってくれないお子さんに困る親御さんは、たくさんいらっしゃいますよね。
笠井:うちもそうでした。
下村:この状況のときに言ってもやらないですし、自分からやる日が来るとは思えないですよね。この場合は、「宿題なんかやりたくないよね」と寄り添います。その上で「宿題はおやつの前にする 、おやつの後にする 」ということを選択をさせます。「寄り添って、選択をさせる」という2段階のテクニックを使うと、自らスッと宿題をやります。
笠井:実際に「やるようになりました」という声を受けてるのでしょうか。
下村:そうですね。そういうお声を、たくさんいただいています。
笠井:20年前に、今の話を聞きたかったです。病院に勤務されていた経験と想いから、育児アドバイザーという道に進んでいると思うのですが、病院では何を学びましたか?
下村:1番印象に残っているのが、お子さんの看取りのシーンですね。0歳から小児がんで入院し、9歳のときにこの世を卒業した男の子がいました。その男の子は、最後のときに一生懸命意識も保ってお母さんに「ママ、僕もう頑張らなくてもいいかな?」と聞いたのです。そのとき、お母様は「ダメ。もっと頑張りなさい」と叱りました。それが最後の会話になりました。それを見たときに、ご家族が本当に愛し合って大切に思い合っていることは、よくわかるのですが、「この経験がお母様の中で今後どうやって根付いていくのだろう」と考えた際に、私の中にしこりのようなものが残りました。
笠井:そうですか。
下村:本当は「愛してるよ」、「ありがとう」と伝えたかったと思う日が来るのではないかと思いました。でもこれは私の意見で、このようなことを言う立場にはないのですが、しこりがある以上、私の経験として伝えていく使命があると考えています。
笠井:しこりを残さない生き方もあると伝えたいということですね。
下村:はい。それが今の活動の原点になってます。

笠井:そうですか。病院で働く中で、「こうあるべきだな」というところも、経験されているのでしょうか?
下村:もちろんです。お子さんのある男の子が、もう助からないというとき、ご両親が微笑んでいらっしゃいました。ご両親は、「この子は神から与えられた子です。この子に最高の幸せのエネルギーを祈ってください」と医者や看護師に言うのです。そして医者や看護婦に対しても、「あなたたちが最高の力を発揮できるように、僕たちは祈っています」とおっし
ゃっていました。本当に穏やかに愛と感謝を伝え合って、ときには笑顔を見せながら送り出す患者さんもいらっしゃいました。
笠井:やはり心の持ちようなのでしょうか。 下村:そうだと思います。
笠井:その最後のシーンから、その考えを子育て全般にも活かせると思ったわけなのですね。
下村:そうですね。私は、子育ては親にとって最高の自己啓発だと思っています。例えば、「嘘つきはだめ」と考えている人がいる場合、同僚や友人が嘘をついても、距離を取ったりできますよね。しかし、我が子が嘘ついたとき、関係を切ることはできません。そのため、親は自分の信念と向き合う必要があります。そこから生き方や感情を認めるというところが始まるため、子育ては自己啓発だと思っています。
笠井:その考えがわかる気がします。私も、子どもに「そんな汚い言葉使わない」と言ったときに、「お父さんだってお母さんにそういう言葉使ってるじゃないか」と言われたことがあります。
下村:お子さんは、結構ドキッとすることを言いますよね。だから、そこをクリアしたら、人生が生きやすくなると思っています。
笠井:仕事をしていて嬉しい瞬間はどのようなときですか?
下村:受講生さんたちが、気付きを得られたとき、パッと表情が明るくなる瞬間があります。その瞬間を見たときや、「学んだことを子どもに試したら、このような反応が返ってきました」と弾むような声でご連絡いただいたりすると、すごく嬉しいですね。
笠井:そんなに難しいことではないけれど、教えてもらうことで、子どもに対するアプローチの仕方があると気がつけるということですね。
下村:受講生は、本当に努力家のお母さんが多いです。頑張って頑張って、それでもダメで、「まだ学びたい」とおっしゃるのですが、私は「もう頑張るのはやめて、努力より正しい工夫をしましょう」と伝えています。今までやったことが、しっくりこないのであれば、違うやり方を試してみて、ダメだったらまた別の方法を試すことが大切です。
笠井:今日お話を聞いて、その2年半の間、受講するためにお客さんたちが待っていたということが、分かる気がしました。これからも、迷えるお母さんや、いろいろなことに悩んでいる人たちの、助けになってあげてください。
下村:はい。ありがとうございました。