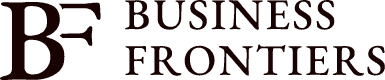9月29日(月)配信 株式会社成和建設 代表取締役 川口敏

1961年、大阪生まれ。武蔵野美術大学を卒業し、その後はデザインの仕事に従事する。仕事が落ち着き、リフレッシュしていた際、知人から誘われ、施工管理を専門とする総合建設業の株式会社成和建設に入社。2016年に代表取締役に就任し、現在に至る。
眞鍋 :今日は、ビシッとスーツで来てくださいましたが、普段から、お仕事はスーツスタイルですか?
川口 :そうですね。弊社は建設会社ですけれど、私が現場に出ることはあまりありませんので、だいたいスーツを着ています。
眞鍋 :すごくお似合いです。
川口 :ありがとうございます。
眞鍋:まず、成和建設さんの事業内容について教えてください。
川口 :建設業もいろいろありますが、弊社は施工管理を専門としています。担当させていただく工事というのが、鉄筋コンクリートや鉄骨造の大きなビルを建てるという仕事になります。それの施工管理ですので、「管理をする」というのが、弊社の仕事になります。
眞鍋 :建設業に馴染みのない方だと、施工管理というと、具体的に現場でどういうことをしているかわからない方も多いと思いますが、どのような仕事なのでしょうか?
川口 :そうですね。施工管理の「管理」というのは「何を管理するのですか」とよく聞かれますが、設備をきちんとしたものを取り付ける、手順を守って作業を進めていくなど、安全の基本を管理することが、何より大切です。その安全を守りながら工程や品質、働く環境、予算なども管理しています。
眞鍋 :映画で言うと、監督やプロデューサーみたいな感じですかね。
川口 :そうですね。子どもたちに施工管理の仕事を紹介するときには、「野球や映画の監督のような仕事」あるいは「オーケストラの指揮者のような仕事」という説明の仕方をします。
眞鍋 :すごくイメージが湧きました。会社は、どちらにあるのですか?
川口 :東京都の北区赤羽です。
眞鍋 :赤羽、いいところですよね。川口さんのご経歴を拝見したのですが、大学は美術大学で学んでいたのですか?
川口 :はい、武蔵野美術大学でデザインを専攻してました。
眞鍋 :デザインと建築というのは、全く別の分野のような気がします。
川口 :私もそう思っていました。ただ、武蔵野美術大学の隣の教室は建築学科でしたし、私も学校で建築の歴史など、いろいろな西洋の建築様式などを勉強していました。しかし、その当時は、今のような建設工事業に入社するということは、想像もしていなかったですね。

眞鍋 :では、なぜ成和建設の方へ進まれたのでしょうか?
川口 :それは、たまたまです。もともと、デザイン畑で仕事をしてまして、デザインや広告の制作などを行っていました。ただ、そもそも仕事に対して、あまり真面目ではなかったですね。
眞鍋 :そうなのですか?
川口 :遊んでばかりいましたので、一つ仕事をやり終えて遊んでいようかということで、本当にしばらく仕事しないで遊んでたのですが、周りから「遊んでいちゃダメだぞ」と言われましたね。そして、「人を探しているところがあるから、そこの社長と会ってみなさい」と紹介されたのが、成和建設でした。
眞鍋 :すごい話ですね。でも、それで入社されて、代表取締役社長に就任されたのですよね。成和建設さんの特徴は、何かありますか?
川口 :なかなか難しいのですが、そもそも建設業は、設計図や計画があって、きっちりと工程を守っていく、きちんと約束事を守っていくということが、建設業の一番大切なところになります。そのため、誠実に真面目に仕事に向き合う会社だというところは間違いないです。
眞鍋 :これから、新たに力を入れていきたい事業などはありますか?
川口 :今、成和建設の全社的なテーマとして、デジタル化、DXというものに取り組んでいます。
眞鍋 :DXに取り組んでいるのですね。
川口 :もともとは、あまり意識していなかったのですが、いろいろなアプリや情報共有のシステムを取り入れるなど、少しずつ進めてきました。振り返ってみれば、あれが「デジタル化だった」という感じでした。建設業というのは、大体どこの国でもそうですし、歴史のどこを切り取っても、その世界のその時代の最先端の技術というものが集約されています。その国の文化やアイデンティティを象徴するような大きなものを作るのが、建築の世界観であると思っています。そういう視点で見ても、建設業では、IT化、デジタル化が、進んで取り入れられています。まだ実験的な形で試験的な導入というような技術もありますが、弊社もデジタル化に、積極的に取り組んでいこうと考えています。

眞鍋 :実際に新しいものを取り入れていくというのは、昔からやられていたのですか?
川口 :私はやりたかったのですが、社員の抵抗もあり、上手く進みませんでした。昔からこのやり方をしていたから、新しいツールはいらないという意見もありますよね。
眞鍋 :そこを説得するのは大変そうですよね。
川口:最近、私自身が反省したのですが、全て新しいものを入れればいいというわけではないと気づきました。なぜなら、新しいものが全て良いもの、会社にとって便利なものとは限らないからです。私自身も、その辺はまだ整理できていなかったですし、デジタル化を進めていく、新しい技術を取り入れていくことで、どのような働き方になるかというビジョンを、社員に説明できていなかったと感じています。不安要素が多い中で、新しいことを取り入れると、社員も反発しますよね。時間はかかりましたが、社員の意見があったからこそ、ここまで進めてこれたと思っています。
眞鍋 :今の従業員さんの反応はどうですか?
川口 :「社長がまたやってるよ」と思っていると思います。
眞鍋 :そうなのですね。新しいものを入れて、変わった、便利になったという声はありますか?
川口 :そうですね。現場の人たちと話をしていると、こちらも改めて気づかされることがあります。私は、「これを入れたら便利になるだろう」、「こういうやり方だと楽になる」と考えていたのですが、現場の目線で見ると、利便性が上がるものと上がらないものがあるようです。やはり、彼らには「良いものをお客さんに届けたい」というこだわりがありますので、新しい技術を伝えますが、実際に使ってもらってから、取り入れるかどうかを検討しています。こちらが思う便利なものと、彼らが使ってみて、「これだったらいける」というものは違いますので、日々勉強ですね。
眞鍋 :川口さんの入社の時のお話を伺ったときも思いましが、社員に「これをやりなさい」と言うタイプではなく、多分本当にいろいろな方の意見を聞きながら、社員にとってのベストを探していくというのが川口さんのスタイルなのですね。
川口 :そう言ってもらえるとありがたいです。社員には、また思いつきで勝手なことをやっていると思われていると思います。でも、弊社の場合は、社員が技術的にも腕のいい人が揃っていますし、優しく優れた人たちですので、いろいろなことを教えてもらいながら、上手に私を利用してうまく会社を発展させてくれているのだと思います。
眞鍋 :そうですか。本日はありがとうございました。
川口 :ありがとうございました。