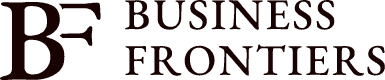11月25日(月)配信 岩本内科医院 理事長 岩本英希

1981年生まれ。2005年久留米大学医学部卒業、その後同大学病院消化器内科に入局。同大学院ではがんの血管について研究を行いながら、肝臓がんのカテーテル治療に従事。2012年、スウェーデンのカロリンスカ研究所に留学。のち、父の急逝に伴い、2014年に岩本内科医院理事長に就任。日本に一時帰国をしたが、再度スウェーデンへ。2015年、日本帰国。久留米大学消化器内科助教、岩本内科医院理事長を兼任しながら、肝臓がんの基礎研究、後輩指導や患者治療を行う。
笠井:本日のゲストをご紹介しましょう。岩本内科医院理事長、ガンちゃん先生こと岩本英希さんです。こんにちは。
岩本:こんにちは。
笠井:本日は九州からお越しいただきありがとうございます。お仕事は何を専門にされていますか?
岩本:基本的には消化器内科医として、特に肝臓がんや転移性の肝がんを含めたカテーテル治療を専門にしています。
笠井:どのような患者さんが集まる病院ですか?

岩本:2種類の患者層があります。1つ目は地域の患者さん。当院では採血、検査からCTまでできるため、すぐに検査や診断が可能な点が魅力です。2つ目は、これ以上の治療が難しいといわれたがん患者さん。そのような方々が全国から当院に治療を受けに来ることがあります。
笠井:セカンドオピニオンを求めて来られるということですね。先生の経歴を拝見すると、肝臓がんのカテーテル治療の道に進んでいらっしゃる。肝臓がんのカテーテル治療とは細い管をどう使うのでしょうか?
岩本:そもそも全てのがんは動脈から血液をもらっているため、動脈から薬を流すことが最も効率よくがんを治療することができるはずなのです。しかし、動脈は体の奥深くにあるもの。だからこそ、動脈まで到達させるためにカテーテルの技術を活用しています。
笠井:カテーテル治療も研究される中で、スウェーデンに留学を経験されている。これは何故でしょうか?
岩本:私は大学に所属し、基礎研究をしています。研究テーマはがんの血管。そこで、スウェーデンのカロリンスカにある研究所にがんの血管研究の権威がいるため、2012年から留学しました。
笠井:先生は久留米大学では助教、さらに岩本内科医院では理事長も務めていらっしゃる。いくつもの草鞋を履いていてお忙しいでしょう。
岩本:忙しいです。
笠井:お若いからできていると感じますよ。

笠井:現在、先生はどういった点に力をいれていますか?
岩本:患者さんの傷を総合的に癒すことです。患者さんの「患」という漢字は心に串が刺さる形ですよね。また、患者さんのことをペイシェントと呼びますが、これには耐え忍ぶという意味があります。そして、「忍」も心に刃と書きます。まさに患者さんとは、心に尖った物が刺さっている状態なのです。病気を治せば尖ったものは取り除けますが、治せない病気もあります。それでも、心の串を抜く医療があると私は信じており、その信念をもとに患者さんに接しています。
笠井:すると、岩本内科医院で表情が変わっていく患者さんもいるのではないでしょうか?
岩本:おっしゃる通りです。受付や事務の方々が親身に患者さんのお話を聞いた上で私も接すると、段々表情が変わっていきますね。当院のスタッフ全員でがんを治すだけでなく、心に刺さった串まで抜けるように毎日頑張っています。
笠井:感動しました。
岩本:ありがとうございます。
笠井:岩本内科医院が多くの患者さんに喜ばれる理由が分かりました。一方で、厳しい状況の患者さんと向き合うこともあるでしょう。そのような患者さんたちの声を聞いて、よかったと思うのはどのような時ですか?
岩本:やはり、表情が変わっていく点ですね。
笠井:まさに、がん患者さんにとって大事なこと。困難な状況にあって、急速に治るわけではないものの、表情が変わるんですよね。
岩本:そう思います。今はインターネットの時代で、自分の病気の情報を簡単に調べることができますよね。しかし同時に、患者さんは取捨選択できずに背負うものが多くなってしまいます。その重圧をプロフェッショナルである私が背負った上で情報を提供すれば、心は軽くなるはずです。私は患者さんに「がんはどこに転移するのが一番危険ですか」と話すことがあります。最も危険なのは、心なのです。心まで侵されてしまうと、同じ期間を過ごすとしても不安や恐怖に押しつぶされ、輝いた時間を過ごせなくなってしまいます。がんの転移を完全に抑えることは難しいのですが、心だけは本人次第で入り込ませないようにすることができる。この心構えを大切にしてもらいながら、私は医療を提供しています。
笠井:本当に大事ですよね。
笠井:それでは3つのキーワードで質問をしていきます。一つ目のキーワードはモチベーション。先生の仕事のモチベーションはどこにあるのでしょうか?
岩本:笠井さんが本に書いていましたが、引き算の縁と足し算の縁を大事にしています。父が亡くなった際には、引き算の縁として悲しさがありました。一方で、当時助けてくれた当院のスタッフや大学の同僚、そして家族など、足し算の縁のありがたさも感じました。それ自体は父が残してくれたものなので、いただいた縁をいかに発展させていくかと思う次第です。
笠井:二つ目のキーワードは信念。先生の信念はいかがでしょう?
岩本:当院の理念は最良の医療を提供し、社会貢献を目指すこと。最高の技術を前提に、心の医療をしっかり提供できているかを考え続けることが大事だと思っています。
笠井:そして第三のキーワードは未来へのビジョン。岩本内科医院が今後目指しているのはどんなことでしょうか?
岩本:技術と心の医療という点については、まだ成長段階にあると感じています。今後はさらに系統的に、個々人の患者さんにあわせた形で進めていきたいです。そうすることで一定の効果が得られ、さらに広めていくことができるはずです。現在では、がんに直接カテーテルで薬が流せるデバイスなど、新たな医療技術が開発されています。その技術を活用し、全身抗がん剤治療が難しい患者さんのために、肝臓以外の場所にもアプローチしていきたいです。
笠井:がん経験者として、今日のお話は染み入るように聞かせていただきました。ありがとうございました。