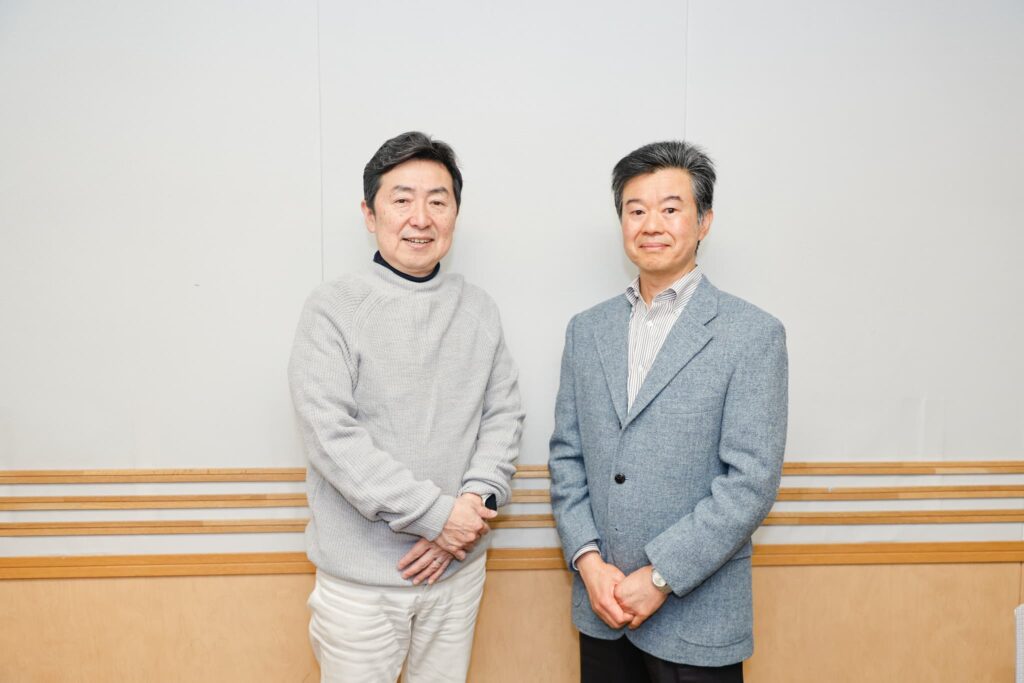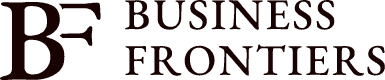1月20日(月)配信 みやざわ耳鼻咽喉科 院長 宮澤哲夫

実家が薬局を営んでいた影響で昭和大学薬学部に進学し、薬剤師免許を取得。その後、一度製薬会社に就職をするも、就業後の時間を使って再度受験勉強をし、帝京大学医学部に入学。主任教授・鈴木淳一先生の紹介でスウェーデンのイエーテボリ大学を訪問した経験から耳鼻咽喉科の道を選ぶ。平成17年に独立、みやざわ耳鼻咽喉科を開業。
笠井:埼玉県春日部の耳鼻咽喉科。場所は具体的に言うとどちらになるのですか?
宮澤:東武鉄道の春日部駅の西口から大体徒歩2分のところにあります。
笠井:宮澤院長の経歴が、昭和大学の薬学部を卒業されて薬剤師の免許を取られてるということは、薬剤師としての人生かと思いきや、今、耳鼻咽喉科の院長先生をやっていらっしゃる。これはどういうことなのですか?
宮澤:実家が町の薬局店を営んでおりまして。母親が薬剤師の資格を持っていましたので、私も薬剤師になるものだと思っていました。子どもの頃から理科も好きで、そのまま薬学部に進んだのですが、入った大学が昭和大学というところで、ここは医学部・歯学部・薬学部が非常に近しい医療系の総合大学でしたので1年生の教養課程は医学部・歯学部・薬学部ともに同じカリキュラムでした。
また、卒業論文も医学部の基礎の研究室で書くことができるというカリキュラムでした。
笠井:先生は何を?
宮澤:薬理学教室で、薬の効き方についての論文を書きたかったのですが、そこは非常に人気で、私は抽選に敗れてしまいました。その時、薬理学の教授が「医学部の生理学教室で似たような研究をしているから、そこに行ってみたらどうか」とおっしゃってくださり、そのまま医学部の生理学教室で卒業論文のための研究をしました。
笠井:周りはお医者さんの卵の皆さん?
宮澤:そこは呼吸生理というのをやっていまして、医学部大学院生の先生は動かなくなった手の神経を呼吸筋の神経と繋ぎかえて、手が動くようにしていくという研究論文を書いていました。しかし、薬学部学生の実験は動物実験なのです。私の研究はネズミを一匹殺すと一例。
一緒にやってる医学部大学院生は、患者さんを一人助けて一例。そちらの方がいいなと次第に思うようになりました。
笠井:面白い話ですね。お医者さんの道もいいなと思ったのですね。しかし医師免許持ってないじゃないですか。それで、この帝京大学医学部というのが出てくるのですか?
宮澤:一度製薬会社に就職はしたのですが、いわゆるジェネリックを作る会社で、先発品を分析して、同じデータが出るような製剤を考えて作っていく。ジェネリックですから、あまり創造的ではなくて、決められた時間に決められたデータを出すような感じです。仕事にあまりモチベーションを持てなかったのと、仕事が終わってからの時間を持て余したので、もう一回その時間で受験勉強をして、もし医学部に入れたら、「自分の人生を勝ち取ったと思おう」と思い、一回だけトライするつもりで医学部を受験して、帝京大学に入ることになりました。

笠井:それで、医師免許取得になるわけですね。最終的に耳鼻咽喉科に進んでいらっしゃると思いますが、ここも何かきっかけがあるんですか?
宮澤:何でも極めれば面白いんだろうなと思っていまして、家系も医者ではないですし、何科でも良かったのですが、たまたま入っていた英語のクラブの顧問をされていた先生に紹介された体験留学ですごく刺激を受けました。あとはスウェーデンのイェーテボリ大学から帝京大学に来ていた学生さんと親しくなったのですが、卒業の時に耳鼻咽喉科の主任教授だった鈴木淳一先生から「君は将来どうしたい?」と聞かれ、「もしうちに来てくれたら、入局の前にもう一度海外の大学を見に行っていいよ」と言われました。「世界中どこの大学でも僕は顔が利くから、どこにでも紹介してやるよ」とおっしゃってくださり、それじゃあ留学生が来ていたイェーテボリ大学に行ってみたいと言いました。先生はその場でその大学の知り合いの教授にファックスを送ってくださり、「ちょうど研究会をやってるから勉強してきなさい」と。それを聞いてこの先生についていくしかないなと感じて、その先生が耳鼻科教授だったので、私はそこで次の人生を探してみようと思い、耳鼻科医になりました。
笠井:最後になりますけれども。これからのビジョン、どんなことをお考えですか?
宮澤:医者と患者の関係は、昭和の時代は「お医者様」と「患者さん」という関係でした。これが平成になると、今度は医者は接遇を頑張りましょう、ということで「患者様」と「お医者さん」の関係になりました。しかし、これは主体が逆転しているだけで、決して医者と患者の間の溝が埋まったわけではないと思うのです。医者は知識を使いながらいい医療を創る。患者さんの方も、どうやったら自分の必要な情報が得られるかを考えながら診療を受けていただけるといいなと思っています。言葉で言えば、「患者力」。患者として、自分が何をやりたいかを考えながら、いい医療を共に創るというような世の中が来る。そういうことができたらいいなと思っています。

笠井:患者力、面白い言葉ですね。これは患者の方が、お医者さんが何を聞きたがっているかを考えるということなのでしょうか?
宮澤:昔は一生懸命話を聞いて、時間をかけても最善を尽くすのが一番いいことだと思っていたのですが、それをやってると、最後の患者さんを見るのが22時を回ったりすることもあるんです。そんな時間に来る人は社会的に弱者の患者さんで、例えば母子家庭のお母さん。もう子どもが耳から膿を出しながら寝ちゃっていて。
できれば、みんなに診療に協力していただきながら、最後に診察を受ける人のことも考えてもらえるような、そのためにどうやって自分の症状を説明して、何をしてもらいたいか、何を聞きたいかをきちんと考えていただくということ。医者と患者が一緒に医療を作り上げるような世の中にできたらいいなと思います。
あともう一つは、スタッフも一緒に幸せを目指し、幸せになっていただきたいと思っています。うちではスタッフに、コーヒーショップのバリスタさんみたいな立場になってくださいと伝えています。医者と医療技術は、コーヒーに例えれば「豆」にあたる素材ですから、スタッフにはその素材を患者さまにみやざわ耳鼻咽喉科の「医療」としてどのように提供するのか、そのサービスをスタッフが中心になって考えてもらいたいと思っています。
このようなスタンスのスタッフと、医者と、患者。
三者が一つに、上手に噛み合った時に良い医療が作り上げられる。私の医院が地域と患者さんとスタッフとお医者さん、みんなが幸せになれるような組織になれたら良いな、と思っています。