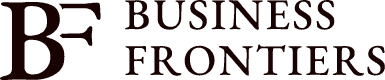3月17日(月)配信 医療法人社団 福寿会 福田記念本宮眼科内科医院 理事長 西村有希子

昭和大学医学部眼科学大学院を卒業し、平成6年昭和大学眼科学教室入局。医学博士号取得。比嘉眼科病院(沖縄)、国立療養所栗生楽泉園病院、富士通病院に勤務。昭和大学病院眼科助手を経て、平成13年7月、福田眼科医院2代目院長に就任。オリコン患者が決めた「いい病院2007年度版」で選任される。平成20年福田記念本宮眼科内科医院に名称変更し、現在昭和大学病院眼科兼任講師も担っている。
笠井:メガネをかけた女医先生ということになりますけれども、この病院は駅の近くなんですか?
西村:そうです。横浜市のJR京浜東北線鶴見駅西口から出てすぐにあります。
笠井:理事長先生ですから、お医者さんでもいらっしゃるわけですよね。経歴を拝見しますと、昭和大学医学部、眼科学、大学院卒業後、本当に眼科一筋なんですよね。福田眼科医院二代目院長に就任しますと、患者が決めたいい病院2007年度版に選出されるということですね。
西村:よく医療雑誌って、ドクター間での紹介とか推薦とかが多いですが、この雑誌は患者の意見で作られたと聞いてます。
笠井:そうですか。この福田眼科医院が今の本宮眼科内科医院になったということですか?
西村:そうです。もともと設立された先生は私の大学の大先輩で、その先生のクリニックを引き継ぎました。
笠井:てっきりお父様が初代で、2代目の院長さんかと思ったらそうではなく、大先輩の病院を引き継いだということですね。
西村:そうなんです。父親はもともと勤務医で、都立病院にずっと務めていまして、最後は大森赤十字病院で定年退職を機に、私と一緒に開業してくれたという感じです。
笠井:ということは、本宮眼科内科院ということで、眼科と内科が併設されている病院ということになりますか?
西村:そうです。眼科と内科の患者様はご年配の方が中心なので、この2つの科が併設されていることは、とても利点が多いと言われています。
笠井:これもしかすると、西村先生は眼科でいらっしゃって、お父様が内科にいらっしゃるのですね。
西村:そうなんです。目は構造上、体の中でも、血管の様子を直接肉眼で観察できる唯一の機関です。よく健康診断や人間ドックでも、眼底の写真を撮ると思うのですが、あれは眼底の血管の形状を見ているんですね。それで、高血圧、動脈硬化、糖尿病など、内科的疾患が見つかることもあります。当院は内科が併設されているので、そういった場合はすぐに連携が取れるわけです。

笠井:眼科でちょっと異常があって、今度は内科行ってくださいね、ということじゃなくて、そのまま受診ができる?
西村:そうです。このまま内科でかかりましょうとご案内します。
笠井:それは便利ですね。
専門的に、眼科と内科って全然別のようですから、やっぱりこれはお父様と西村先生が別の勉強をしていたということが良かったわけですね。
西村:そういうことになります。
笠井:ちょっとこの駅前の病院って聞くと、ちょっとサラリーマンが忙しい中、通う病院っていうイメージがあるんですが、ホームページ見たら、一番最初に「町の診療所としての使命感を胸に」と、どーんと出てるんですよ。これは病院の理念と考えていいのでしょうか?
西村:そうですね。大学病院というのは特定機能病院と言われてまして、地域の中核病院と言われる大きい病院になります。それと、私が今やっている診療所はかかりつけ医とよく言われるんですけども、役割が全然違うと思っています。
最近の国の方針は医療連携を使うことを推奨しているのですが、まずはかかりつけ医で日々のフォローアップを受けてもらって、病状が悪化したり、より専門的な検査や治療、手術が必要になった際に、紹介書を持って中核病院にかかるという流れになっています。
笠井:私はがんになって大学病院に通いましたけど、ほんと混んでて時間かかるんですよね。3時間、4時間コースみたいな。先生は忙しそうにしているので、診療時間が短いのはもうしょうがないですよね。ですから、このかかりつけ医というものが、やっぱり今非常に重要になってきていますか。
西村:そうですね。大学病院はどうしても診察や検査に時間がかかりますし、その分待ち時間がとても長いんです。問診もてきぱきとこなすので、患者様の家庭環境、仕事環境、趣味や思考はかかりつけ医ほど把握できないんですね。
経験上、不調や悩みを外来で吐露するだけで、不安からくる症状が改善することもあります。それこそが、今かかりつけ医の重要な役割なんじゃないかなと思っています。
笠井:そうすると、かなり患者さん個人のバックボーンや家庭環境などをつかんだ上でのコミュニケーションをとるということですか?
西村:そうですね。お仕事の内容や、家庭がどういう状況かで、ストレスがかかる度合いも違いますし、それによって起こり得る病状も変わってくるわけなんですね。それは、やはりかかりつけ医しか把握できないと思っています。

笠井:それが、町の診療所としての使命感という、このホームページにまず掲げている部分なんですね。眼科医として、ターニングポイントとなった出来事は何かありますでしょうか?
西村:私、個人的な話なのですが、大学病院勤務から開業医になって、数年後にクリスチャンになったんですね。クリスチャンになりますと、考え方や日々の姿勢が大きく変化し、診療の上では、それまで病気を治すことで患者様の助けになろうと努力してましたが、クリスチャンになってからは今まで以上に患者様という人を見るようになったと思うのです。クリスチャンの教えには、神様から愛をもらっているように他人に愛を与えなさいってあるんですね。日々の外来で、患者様一人一人に診療を通して愛を与えようと今努めています。
笠井:お医者さんとしての立ち位置みたいなものも変わってくるんですね。
西村:そうですね。
マザーテレサの有名な言葉に、愛の反対は無関心という言葉がありますが、私は愛とは、相手に関心を持って寄り添うことなんだな、と今思っています。患者様に寄り添っていく姿勢こそ、まさにこのかかりつけ医の使命だなと思ってるんです。
笠井:確かに、様々なお医者さんに接してきた中で、この人あんまり僕に関心ないなっていう感じの先生にもあったことがあります。
西村:医療人も人ですので、いろいろなキャラクターがあるんですね。本当に医師と患者さんって、一期一会なんですよね。たまたま担当になった先生が自分と相性がよく、自分に関心を持って話を聞いてくれるかということも重要だと思います。
笠井:それが、よく言う傾聴というやつですね。耳を傾けることが、実は大事なんだと。我々も、がん患者なんか特にそうなんだけど、我慢するんですよ。少しぐらいのことは我慢して、先生に迷惑かけないって思ってるんだけども、そこを聞き出してもらえると、かなり気持ちが軽くなりますよね。
西村:病状は、残念ながら今はすぐ良くなっていなくても、私に寄り添ってもらえてるんだなと思うだけで、心強くなるようで、気持ちが楽になるようです。
笠井:仕事をしていて、嬉しい瞬間はどんな時です?
西村:外来で拝見させてもらって、「先生に見てもらえると、安心して帰れるのよね」と言ってもらえると、患者様に寄り添う愛が届いたなと嬉しくなります。
笠井:そうですか。これからの目標がありましたらお願いします。
西村:かかりつけ医としての使命感を胸に、専門医として、眼科と循環機内科が連携してるんですけども、それを一層連携を高めていきたい。また、スタッフ全員がこの患者様に関心を持って寄り添う姿勢、これをすべてみんなが持つようにする。それが今後の課題ですね。
笠井:なかなか都会にいると良いかかりつけ医を見つけにくいんですけれどもね。そんなふうに出会えている、この本宮眼科内科医院に出会えている患者さんは、ある意味幸せですよね。
西村:そう思ってもらえるととても嬉しいです。