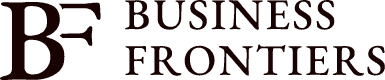5月19日(月)配信 株式会社ユニバーサルシャインいのちの華 代表取締役 兼 管理責任者 大滝ひとみ

仙台の東北労災看護専門学校卒業後、東北労災病院勤務した後、渡米しシアトルのコミュニティカレッジ卒業。帰国後は、大阪の淀川キリスト教病院で勤務。2010年に再び渡米し、州立ニューヨーク大学卒業。その後、仙台の青葉学院短期大学看護学科で助教授として勤務するも大病にて退職。地元に戻り養生しながら、福祉や学校関係に勤務。2020年5月、コロナ禍の中、いのちの華訪問看護ステーションを設立。
笠井:今日は山形から来てくださったのですね。遠いところありがとうございます。訪問看護ステーションのいのちの華は、山形のどちらにあるのですか?
大滝:日本海側の鶴岡市にあります。
笠井:生まれも鶴岡なのでしょうか?
大滝:そうです。
笠井:地元でやってらっしゃるのですね。いのちの華の特徴はどのようなところですか?
大滝:訪問看護ステーションなので、在宅療養したい方、あとはグループホーム、施設などに入っている方が対象で、お願いされたら訪問するという形です。
笠井:そうですか。大滝さんの経歴を伺いますと、看護専門学校を卒業した後、東北労災病院で看護師として経験を積み、アメリカのシアトルに留学されていますが、なぜアメリカへ行ったのでしょうか?
大滝:その頃の日本にはホスピスケアや緩和医療など、そういう言葉の定義すらまだありませんでした。当時は人工呼吸器をつけるなどしていましたが、「それでいいのかな」と感じていました。
笠井:つまり、亡くなっていく方の最後の医療をどうするかという課題ですよね。
大滝:そうです。そんな時、イギリスやアメリカなどで、ホスピスをやっているところがあると知り、軽い気持ちで見に行きました。
笠井:そして帰国後、大阪の淀川キリスト教病院で十数年勤務され、今度はアメリカのニューヨークへ行かれたということですが、なぜ再びアメリカに行ったのでしょうか?
大滝:これは結婚を機に、主人の仕事の都合で行ったのですが、「もう少し勉強したいな」という思いもあり、思い切って州立ニューヨーク大学に入学しました。
笠井:そうだったのですね。帰国後、仙台の青葉学院短期大学の看護学科で助教授として働かれた後、退職され、2020年5月に訪問看護ステーションのいのちの華を設立されたということですが、なぜ訪問看護というスタイルを選んだのでしょうか?
大滝:ニューヨークから帰ってきた時、年齢も重ねていたことに加え、短大で働いてた際に病気になりました。命にかかわるような病気だったため、療養のために地元に戻りました。地元に戻った時に、東北はどこの地域も高齢者が多くなり、福祉や医療など様々な問題があるということを実感したのです。そして、社会のために何かできることがないかなと考えた時に、自分の今までの経験を生かすことができるのは、やはり訪問看護ステーションかなと思いました。

笠井:病院看護ではできないことが、訪問看護では可能になる場合があるのでしょうか?
大滝:ありますね。病院だと「心臓が悪いから動かないでね」とか、「塩分は控えめにしましょう」となります。しかし私は、「少しわがままも聞いてあげたいな」と思っています。美味しいものや大好きなものを食べないで一生を終えるというよりも、少し食べて、家で楽しく過ごしてほしいですね。
笠井:訪問看護における仕事へのこだわりはどのようなところにありますか?
大滝:スタッフにもいつも言ってるのですが、「看護師として患者様のご自宅には行かない」ということです。一人の人間として行って、たまたま看護師だから、医療的な知識、栄養的な知識、リハビリ的な知識があるから、悪化しない程度に本人のやりたいことを尊重し、サポートするという意識で行っています。
笠井:ありがたいですね。一人の人間として関わっていくという中で、これまでどんな事例がありましたか?
大滝:息子さんが寝たきりの高齢のお母さんをみているご自宅で、「もしかしたら今年の秋の紅葉が最後かもしれないから、連れて行きたい」と言われたのです。それで「じゃあ行きましょう」と車に乗り、すごい綺麗な紅葉を見にいきました。
笠井:喜んでいたのではないですか?
大滝:そうですね。息子さんにも喜んでいただきました。

笠井:そうですか。そしてもう一つ、訪問看護として避けて通れないのは、看取りがあると思います。大滝さんは看取りの経験が豊富と聞いていますが、看取りの看護では何を大切にされていますか?
大滝:やはり本人もご家族も、まず穏やかで安心できるというのが大切です。そのために身体的な苦痛や心の不安や恐怖もできるだけ最小限にできるよう心がけています。最後、亡くなったとしても、皆さん寂しくて涙を流されるのですが、そこに「良かったね」と笑って言える場面を作れるようにしています。
笠井:亡くなった後に、「在宅でこんな形で見送れて良かったね」と笑顔になる。そういうことがあるのですか?
大滝:あります。だから皆さん、泣きながら笑います。
笠井:いいですね。
大滝:高齢のお母さんを看取った70歳の息子さんに、「俺も将来お願いしようかな」というお言葉をいただきました。
笠井:自分も何かあったら訪問看護にしたいということですね。
いのちの華の強みは何でしょうか?
大滝:今の日本の医療だと循環器や脳外科など分野が別れていますが、私たちは一人の人間としてトータル的に見るようにしています。また、私が以前勤めていたキリスト教病院では、身体的な側面だけではなく心理的、社会的な側面も考慮する全人的医療を行っていました。そのため、「肉体も精神も社会的なところもケアしたい」といつも思っています。
笠井:そうですか。入院している患者さんを自宅で看護することで、患者さん自身の命は限られているけれど、元気になるとか前向きになることもあるのですか?
大滝:ありますね。以前、病院から「食べられないから、最後は自宅で看取りの方向性で」と言われ退院した高齢の方の看護に行きました。何が食べたいかを聞くと「カレーライス」と答えられ、「家族の方がカレーライス作ってくれるみたいだよ」と伝えると、「じゃあ、まだ生きられるかな」と話してくれました。闘病生活の中にも楽しみを見つけたことで、それからは食事も取れるようになり、今はデイサービスにも前向きに通っていただいています。
笠井:今も元気で、家で介護されてるわけですね。一方で、やっぱり訪問看護には覚悟が必要で、安易に訪問介護にすると、辛い目に遭うという話も聞くのですが、いかがでしょうか?
大滝:そうですね。一人暮らしのかたや、息子さんだけ介護してる方なども、いろんな家族の形があり、さらに経済的な格差もすごくあるので、難しい場合もあります。私たちはそこを見極めながら、ご本人とご家族が今ここに一緒にいられて「嬉しいね」と思ってもらえるようなケアを意識しています。
笠井:そうですか。これからも患者さんへの寄り添いをよろしくお願いします。