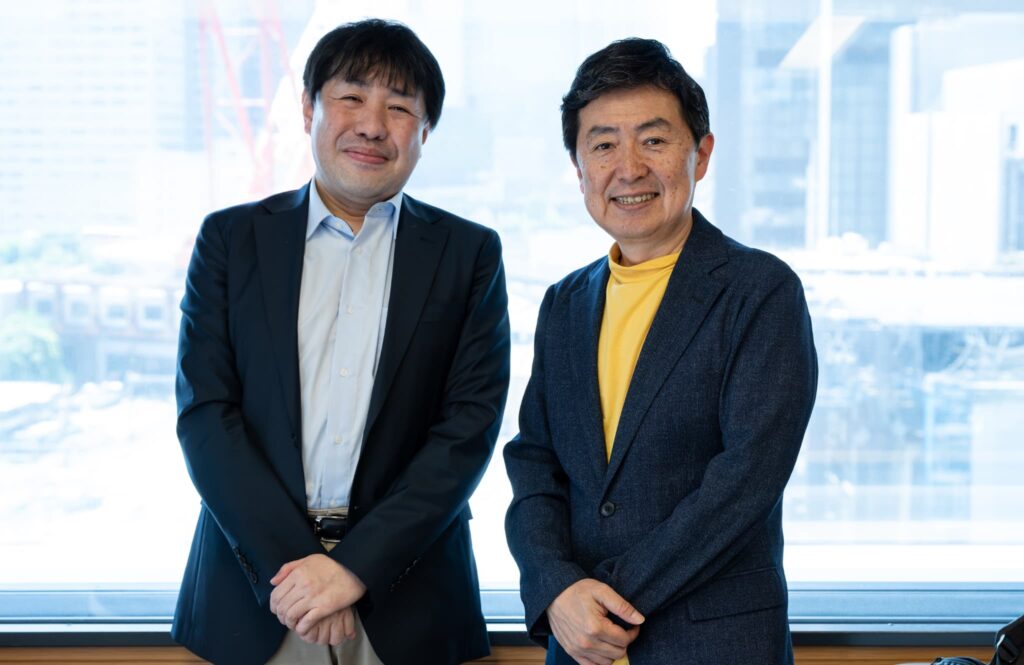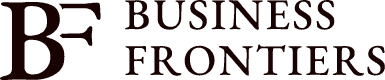6月9日(月)配信 あわざこどもクリニック 院長 田中篤志

ヴィアトール学園洛星中学・高等学校。大阪医科大学(現:大阪医科薬科大学)医学部医学科を卒業後、平成15年京都大学小児科学教室に入局。近畿大学医学部奈良病院、彦根市立病院、京都大学医学部附属病院(大学院医学研究科発生発達医学講座発達小児科学 血液・腫瘍診療グループに所属)、三菱京都病院ほか大学およびその関連施設にて勤務、研鑽を積む。平成29年より公益財団法人日本生命済生会日本生命病院(救急診療センター兼務)での勤務を経て、令和元年に大阪市西区にあわざこどもクリニックを開院。
笠井:あわざこどもクリニックは、大阪の阿波座駅のすぐ近くにある病院ということですが、小児科としての特徴はありますか?
田中:大阪市の中でも、西区は人口が増加している地域の一つと言われており、子どもが多いという特徴のある場所だと思っています。
笠井:田中先生のこれまでの経歴を拝見しますと、今の大阪医科薬科大学医学部医学科を卒業された後、京都大学医学部の小児科学教室に入局され、そして京都大学の大学院医学研究科発生発達医学講座、発達小児科学に所属されています。その後、日本生命病院小児科副部長などの職務を担い、2019年に独立されてあわざこどもクリニック小児科アレルギー科を開設されました。ご自分でクリニックを始められたのはどうしてでしょうか。
田中:15年以上勤務医として働きましたが、次第に自分が理想とする医療と、病院という医療現場で行っている医療との乖離を感じるようになりました。例えば、夜に熱がでるなど困った状況で医療を受けたい場合、救急医療が受け皿となり、病院ではなかなか受け入れることが難しい一面があります。実際に理想を体現できる環境を模索した結果クリニックの開業を決めました。
笠井:開業までの15年は小児科医として働いていらっしゃったのですか。
田中:はい。小児科医として働いていました。
笠井:自分が理想とする医療と、病院という大きな現場の中で働いている医療に少し差を感じたということですね。
田中:そうですね。また、もともと勤務医をしていた時、開業すると病院で見る疾患の状況とは違って、風邪など一般的な疾患がすごく多いと想像していました。しかし、実際に開業してみると、患者さんの訴えは多岐にわたります。大きな病院レベルの症状の患者さんもいらっしゃり、適切に答えてることも求められるなど、想像してたものとは違いましたね。
笠井:小児科の病院がどんどん減っている中、小児科の病院ができることは地域にとってはとてもありがたいですよね。
田中:前の職場のすぐ近くで開業させていただいたので、ずっと見てきた患者さんたちが来てくださることも多かったです。しかし、本当に「期待していただいている」という部分は、開業してからもひしひしと伝わってきます。

笠井:仕事へのこだわりはありますか?
田中:もともと勤務医の時に小児救急に関わることが多かったため、緊急で直接来られた患者さんの状態が悪い場合に状態を安定させ、高次病院につなげるなど、責任を持って対応することを意識しています。
笠井:病院名が「あわざこどもクリニック小児科アレルギー科」ですよね。アレルギー科というワードが入っているのがちょっと面白いなと思いました。
田中:ありがとうございます。勤務医時代に医局から派遣された病院にアレルギーの専門の先生が多くいらっしゃったため、アレルギー疾患を見る機会が非常に多くありました。それもあり、アレルギーは専門としてやっていきたいと考えています。
笠井:そうですか。また、お子さんの心身症に関しても見ていらっしゃると伺いました。
田中:これも偶然僕が勤務してきた病院では、心身症の患者さんを見ることが多かったので、今まで積んできた経験をこれから還元していくという形で、現在注力しています。
笠井:どういうお子さんの状況を見ているのですか?
田中:心身症といっても幅が広いのですが、心と体ということでいうと、やっぱり不登校の問題などが絡んでくる場合が非常に多いと思っています。その不登校にもいろんな理由があります。周りの友達との関係が悪い、それから体の問題でいうと、いわゆる気立性調節障害などもあります。
笠井:それはどういうものでしょうか?
田中:自律神経のバランスが、子どもの体から大人の体になっていく段階で、アンバランスな状態が一時的に発生することがあります。血圧が変動して、朝がすごく辛い、朝起きることができないという症状などです。一昔前は、朝起きれないと「サボっている」と言われましたが、実は病気だった可能性があります。たまたま母校の先生が心身症を専門にされており、私は学生の時に心身症について学ぶ機会がありました。

笠井:あわざこどもクリニックは、心身症専門の診療科はあるのでしょうか?
田中:科としてやってるわけではないのですが、相談は受けています。最近、子どもの全人的医療という言葉がありますが、子ども自身を全て見るようにしています。
笠井:「こどものことなら、とりあえずなんでも見てあげるよ」という構えでいらっしゃるのですね。
田中:そうですね。そのスタンスを崩さないようにしたいなと思っています。
笠井:地域のかかりつけ医の先生が、いろんなことの相談に乗ってくれるというのは、先生も目指してるところなのですね。
田中:やはりそこは目指しています。もちろん自分の専門外や領域を超えてしまった場合は、その道のプロにしっかり振らせてもらいます。ただ、まずはお話を伺い、自分でできる範囲の対応をしていきたいです。
笠井:地域医療としては、本当にありがたいですね。
さて、お医者さんとしてターニングポイントとなったエピソードなどはありますか?
田中:そうですね。学生の時に父が心筋梗塞で亡くなったのですが、それがまだ54歳の時だったのです。その日、父はマラソンに行っていました。僕は大学の先輩方のお手伝いがあったので、後から行こうと思ってた時、「お父さんを救急車で運んでいる」と電話がかかってきました。病院に行った時には、「もうちょっとダメでした」という状態でした。
笠井:そうでしたか。
田中:その状況の中で、当時僕が医学生だと知っていた循環器内科の先生に、「救護所にいた看護師さんが必死に、心臓マッサージ、胸骨圧迫をしていたよ。肋骨が折れるほど頑張っていらっしゃたんだよ」と教えていただきました。当時まだAEDが普及してなかったので、AEDでの蘇生処置っていうのはありませんでしたが、誰かわからない、見ず知らずの人に対して、「これだけ頑張ってくださった方がいた」ということが、やはり自分の医療への思いの礎になったと思っています。だからこそ、どんな子どもであっても、大人であっても、「目の前で倒れてる人がいたら、その人にまずできることする」ということを意識して行動しています。
笠井:最後にこれからのビジョンを教えてください。
田中:もう亡くなってしまったのですが、小児救急の有名な先生がいらっしゃいました。その先生が「100人の救急患者を見るときに、1人だけいる異常のある患者さんを、多忙な中でもしっかり見つけ出すかが重要。だから99人が何もなくて、ただの風邪というような軽い状態でも、その中に紛れている1人の重症の子を見つけるために、100人に真剣に向き合う必要がある」とおっしゃっていました。その言葉は常に意識しています。やはり「どんな時でも手は抜いてはいけない」「どんな時も何かが隠れてるかも」という考えは持たないといけません。そこだけは絶対になくさないようにしています。その中で自分のクリニックでも、そういうことが体現できたらいいなと思っています。