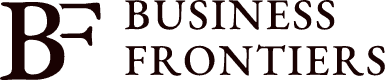1月6日(月)配信 Ultra FreakOut 株式会社 代表取締役社長 宇木大介

早稲田大学を卒業後、SI企業にてエンジニア、営業、マーケティング業務を経て、事業提携やM&A実務を経験。出向先で執行役員CFOを務める。2020年、フリークアウト・ホールディングス執行役員就任、Ultra FreakOut株式会社代表取締役就任、株式会社IRISの代表取締役も兼務。
笠井:Ultra FreakOut株式会社、お仕事はどんなことになりますか?
宇木:デジタルサイネージと呼ばれる情報ツールの、動画配信基盤を開発、運用しておりまして、商品名はMaroonです。
笠井:デジタルサイネージって、いわゆる動く看板というか、今も街中、特に駅なんかにたくさんありますよね。10年、5年くらい前、突然街中に溢れ始めて。その中身を作ってらっしゃるんですか?

宇木:我々は仕組み、中身側になっておりまして。配信する動画は広告代理店や広告主から提供いただいて配信するお手伝いをしています。機械の方はメーカーさんが作られたものを使わせていただいて、我々はその中に収めるソフトウェアを作っています。
笠井:経歴を拝見しますと、早稲田大学を卒業後、まずどんなお仕事に就いたのでしょうか。
宇木: IT企業でエンジニアをやって、そこから転々と職種が変わり、投資やM&Aと呼ばれる仕事にもつきまして、その流れの中で現職の事業に移籍したのが2019年。そこからデジタルサイネージの事業をずっと担当しています。
笠井:どういう広告をやっていらっしゃるんですか?
宇木:一番わかりやすいものですと、全国のタクシーの後部座席に設置されているモニターで流す広告ですね。あとはサウナの外気浴場ですとか、喫煙所内のモニター。変わったところで、オフィスの複合機の上のサイネージなどをやってます。
笠井:いろんなとこでやっていらっしゃるんですね。広告業界において、ものすごい急成長している分野ってことになりませんか?
宇木:そうですね。特にこの5年、コロナ前から現在で、かなり多く増えています。
笠井:急成長してるってことは紆余曲折もあったと思うんですよ。
宇木:やはり、コロナで外出が規制された時はタクシーの乗車が減りますので、人が乗らないからタクシーも動かない。タクシーが動かないということは、広告主様もつかない。こういう悪循環になり、業績がぐっと下がってしまったということがありますね。
笠井:サイネージ事業を軌道に乗せるためにどんな工夫をされてきたんですか?
宇木:一番は、やはり広告だけを流すと注目を浴びるのがなかなか厳しい。見てもCMばかりという風にならないように、タクシーの中だけ、コピー機の上だけでしか見れないコンテンツを挟むことで注目を浴びるようにしました。そうすることで合間に流れるコマーシャルへの注視率も上がっていくといった工夫をしています。
笠井:タクシーでは最近ニュース番組風の動画が流れたりしますが、そういうのも作ってらっしゃるのですか?
宇木:我々の場合は企画だけなんですが、当社の自社番組という形でやっております。
笠井:Ultra FreakOutの強みはどんなところですか?
宇木:タクシーサイネージを配信する仕組みを長年運用してきたことが大きな強みです。それを裏方という形で支えてきたこともあって、先ほどお話したような事業環境が変わった時にどういう風にしていけばそのサイネージを見ていただけるかというところも、我々もノウハウ、経験として持っています。これを、これからデジタルサイネージを始めたいという企業様に向けて提供するわけなんですけれども、単に仕組みを提供するだけではなく、どうやって運用していけばいいのか、どういうサイメージを作っていけばいいのかというところに対するアドバイスをするところは我々の大きな強みだと思っております。
笠井:今まで看板を出していた会社さんに対して、サイネージの動く看板にするといいですよとなりますが、テレビモニターも必要だし、結構お金がかかると思うんですよ。そこはどうなんでしょうか。
宇木:以前と比べると、モニターの価格も随分下がっていますし、広告が入ることで、実際にそのハードウェアの投資の回収というのもしていけるような、そういう運用モデルを作っていけるかなと考えてご提案しています。

笠井:仕事をしていて嬉しい瞬間ってどんな時ですか?
宇木:やはり我々が設置したサイネージを見てらっしゃるお客様の姿、それを見ていただいているっていうのを実際に私の目で見ることができた時、これはかなり嬉しいですね。
笠井:お客さんが素通りするのか、立ち止まるのか、ありますよね。でもそれって中の広告を作っている人のセンスでもあるじゃありませんか。そことはどういう連携を取ってるんですか?
宇木:そこは線引きが難しいところではあるんですけれども、世の中今かなり個人に最適化された情報が出る、みんな興味のあるものばっかり出るんですね。で、サイネージというのは、パッと見た時に何かが流れいてる。その流れているものに意識が向く、新しい気づきを得る媒体だと思ってるんです。なので、通りすがった時にそれを見ている姿っていうのは、我々が目指していることが体現できているということだと思っているので、クリエイティブの良し悪し云々ではなく、サイネージっていう媒体に接触した人が興味を持ったという捉え方を我々はしています。
笠井:それはよくわかります。インターネットの世界は自分の好みの広告が出る仕組みで広告量は伸びています。けれども、自分の好きな情報だけが集まってると新しいものに接触できない。我々テレビっていうのはまさにそこなんですよ。ぼーっと見てたら知らないものができたとか。新聞もそうで、自分が読みたい記事を読んでるけども、なんとなく開いたら出てくる情報に気づきがあるんですよ。デジタルサイネージって新しいようで、その基本的な情報の接触に立ち返っているんですよね。
宇木:我々が目指してるのはやっぱりそういったところですね。
笠井:それは大事ですよね。視野が狭くなっている今の世の中ですから。その感じにちょっと今ハッとさせられました。経営理念はどういうところにあるんですか?
宇木:外部の環境の中で新しい情報に接触するようなきっかけを作るというのが一つの事例になると思うんですけれども、ITはそういった気付きを与えるためのツールだと思っています。ですので、そういったものが一人ひとりに対して新しい情報を提供し、その提供した情報をもとに新しいビジョンが出来上がって何かが生み出されていく、社会の未来が出来上がっていく。そういうようなものを我々の理念として会社を運営しております。
笠井:これからのビジョン、どんなものがありますか?
宇木:元々FreakOutという名前が、度肝を抜くという意味合いがあるんですけれども。サイネージの分野で度肝を抜くようなものを作り上げていく、それを我々が、あるいはそういうことをしている企業様をご支援させていただく、そういった形で関わっていくというのがこれからのビジョンとなっています。昭和の時代の街頭テレビのように、わざわざ見に行くサイネージを作っていくっていうのを目指したいですね。
笠井:実際にそういうサイネージって出始めてます?
宇木:他社様の事例ですけれども、新宿にある飛び出す3Dサイネージのように。
笠井:あの猫のやつですよね。あれびっくりしますよね。
宇木:ああいうものを我々も作っていきたいなと。我々も知恵やノウハウ、経験などを生かした、ああいう度肝を抜くサイネージを作りたいと思います。